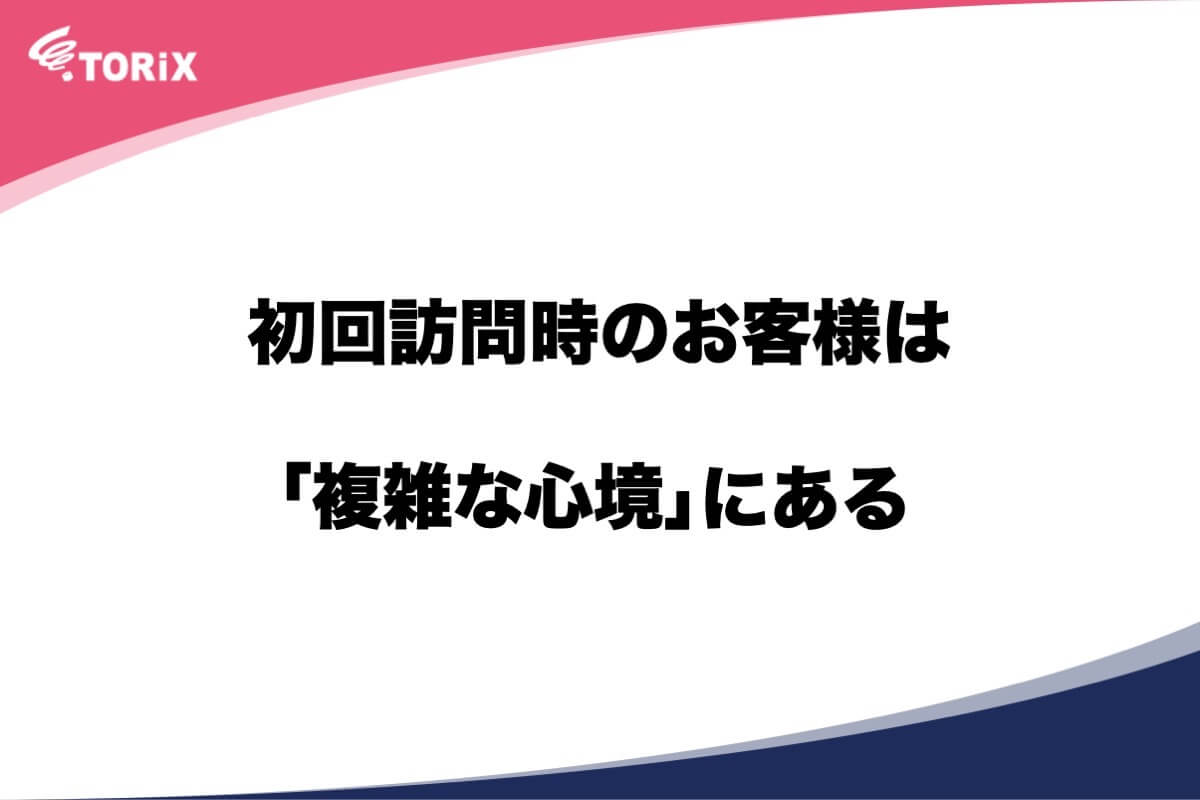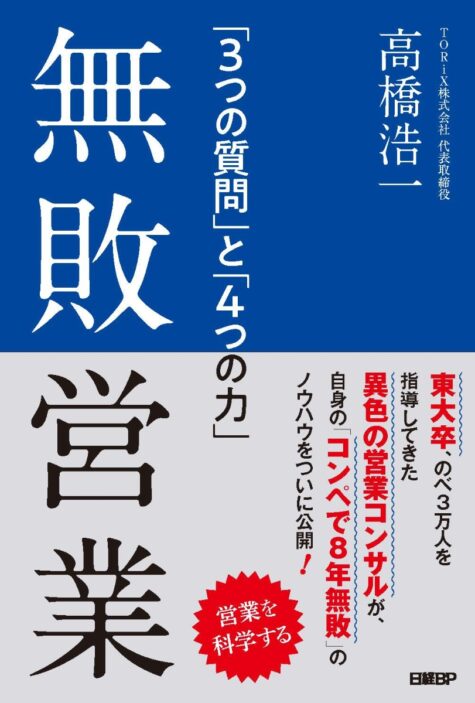初回訪問時におけるお客様の心理
営業の初回訪問から次のステップに進むには、「初回訪問時におけるお客様の心理」を理解することが重要です。特に重要なのは、「誤解に基づいた判断をされないようにすること」です。
初回訪問におけるアポイントには2つのパターンがあります。
①お客様が望んだわけではないアポイント
「お客様が望んだわけではないアポイント」には、コールドコールからのアポイントや、インサイドセールスによる掘り起こしによって生まれたアポイントなどがあります。
このパターンのアポイントは、お客様からすると次のようなイメージです。
![]()
お客様
何かよくわからないけど会ってみるか。まあ、とりあえず時間は空いているし、なんか一生懸命だし…
このアポイントは、商談当日になるとお客様の中で次のように変わります。
![]()
お客様
あれ、カレンダーに入っているこの件なんだっけ?(メールを検索すると)…ああ、「売り込み」ね。でも今日は忙しいんだよな。なんでこのミーティングを入れたんだろう…有用な情報がなければ、失礼のないようにさっさと終わらせて仕事に戻ろう。
お客様の心の中は「有益な情報はあるのか?なければさっさと終わらせたい」となっています。
しかし、お客様には「これに関する情報がほしい」という明確な意識があるわけではありません。お客様は「有益な情報がほしい」という漠然とした気持ちでいるのです。
そのため、冒頭に「今日は情報収集ですので…」と言われたアポイントで単にサービス紹介をしても、それがお客様にとって有益な情報でなければ響かずに終わってしまいます。
お客様は以下のように一見すると矛盾した気持ちを抱えています。
- ①早く商談を終わらせたい(見切りたい)
- ②でも何らかの良い情報はほしい
往々にして先に①で引っかかってしまい、商談が終わってしまうことが多いです。その際、お客様は「見切ること」自体が目的化し、「品定めモード」になっているため、まずはこのモードを外すことが必要です。
「品定めモード」を外すには、以下のいずれかにしかチャンスはありません。
- アポイントが決まってから当日を迎えるまでの間
- 商談冒頭の3分間
可能であれば、当日を迎える前に「質の悪い売り込みとは違う何か」を提示するようにしましょう。商談前の電話やメールをおそろかにしないことが重要です。
初回訪問前にお客様に伝えるべき情報は以下の通りです。
- お客様のことを最低限、調べていること
- お客様にお役に立てる理由があること
- 今のタイミングでお客様にお役に立てること
- 他のよくあるベンダーと違う点
- 「めんどくさい営業」ではないこと
「初回訪問前に伝えるべき情報」を伝えた後は、「アポイントが決まってから当日を迎えるまでの間」か「商談冒頭の3分間」のいずれかの時点で、お客様に「今まで様々な取り組みをしてきたにも関わらず、解決されないまま残っている課題」を聞きましょう。これを掴まずにいきなり商品説明をしても、お客様からすぐに切られてしまいます。
誤解に基づいて「ああ、やっぱり違ったか」と判断されてしまうのです。お客様は一刻も早く「この場を終わらせて仕事に戻りたい」という気持ちがあるため、バイアスも働きやすくなります。
②お客様が望んだアポイント
お客様が望んだアポイントには以下のようなパターンがあります。
- お客様自身が資料請求をされた
- お客様がウェビナーに参加して、もう少し話を聞いてみたいと思った
- お客様からの自発的な問い合わせ
この場合、お客様は「前向きモード」なので、営業からすればやりやすいです。
しかし、この場合でも注意すべき「落とし穴」があります。
お客様が望んだアポイントといえども、以下のような「ギャップ」が存在しています。
- お客様は自社のことをよく知っているわけではない
- こちらもお客様のことをよく知っているわけではない
そのため、①と同様に「アポイントが決まってから当日を迎えるまでの間」か「商談冒頭の3分間」で、お客様のことを理解するための質問をしておきましょう。
①と異なるのは、「お客様が話してくださるモード」になったら、自社の話をする前に、とにかくとことんお客様の話を聴きに回ったほうが良いということです。
ここで「せっかくお時間をいただいているのだから、さっさと自社の紹介をしないと」と焦ってしまうと、ズレが起こりやすいです。
お客様がアポイントを望んでいる場合、「何かに困っているが、それが解決されていない」ため、いったいそれが何なのかを明らかにしてから自社の紹介をした方が深く響きます。 お決まりのルーティーンで「資料請求された背景を教えていただけますか」と一言聞いた後にすぐ自社の話をしてしまわないよう注意しましょう。
お客様が望んだアポイントでも、お客様は次のような状態です。
![]()
お客様
なんか役に立ってくれそうだな。でも、具体的に何をしてくれるか、よくわからない。
そのため、自社に対して何らかの「思い込み」や「先入観」が発生している可能性があります。ここで期待ギャップや誤解の種があったら、早めにそれを摘み取っておくようにしましょう。
お客様に働いている「カラーバス効果」を意識しよう
お客様には相反する感情があります。良い情報や提案を受けられる機会があれば嬉しいと思う一方で、商談は手短に終わらせたいという気持ちもあり、これは一見矛盾しているように見えます。
ここで注目すべきなのが、カラーバス効果と呼ばれる現象です。これは、特定のものを探していると、それに紐づく情報が目に入りやすくなる現象のことです。例えば、ピンクという色を頭の中に思い浮かべると、その後ピンク色のものが特に目に飛び込んでくるようになります。通常であればピンク色のものは特別意識されないのですが、一旦そのイメージを持つと、ピンク色に見えるものが優先的に認識されやすくなります。
初回訪問時においてもお客様にカラーバス効果が働いています。それはどのようなものかというと、お客様は「この営業から詳しく話を聞く価値はない」と思える情報を探しているのです。
もちろん、お客様は良い情報を探しています。しかし、お客様には「資料さえもらっておけば、後は自分で見ることができる」という心理があるため、「この営業から詳しく話を聞く価値はない」と思ったら、「資料だけもらっておこう」という判断になるのです。
「資料だけもらっておこう」という落としどころになりやすい理由には、書籍『無敗営業 「3つの質問」と「4つの力」』(日経BP)でもお伝えしているように、基本的には「6人中5人はがっかりさせられる営業で、6人に1人が『また会いたい』と思わせる営業である」ということが挙げられます。つまり、買い手側の立場からすると、また会いたいと思える営業に出会う確率は非常に低いのです。そのため、半ば諦めの気持ちもあってか、お客様は「どうせこの営業も大したことはないだろう」という低い期待値から商談に臨むことになります。
重要なのは「価値提供するポイント」をもらうこと
ただし、お客様の気持ちは複雑です。「もし仮にこの営業が優れた営業だったらラッキーだな」「そうであれば、もう少し時間を割いて話を聞いてもいいか」という期待も同時に存在しています。そのため、お客様としては時間を割くだけの価値があるかどうかを見極めようとする気持ちが働きます。
しかし、お客様は「忙しくて早く仕事に戻りたい」という状況にあります。ほとんどのお客様は、期限の迫ったタスクが山積みになっている状態にあるのです。
お客様にとって、目の前の営業が優秀かどうかは不確実です。このような状況では「この営業から聞けることはこの程度だろう」と判断したら、「すぐに仕事に戻ろう」という方向に流れやすくなります。
つまり、営業はお客様の「ジャッジする目線」を意識する必要があるということです。欠点探しをしようとしているお客様に対して、営業の些細な仕草や言動は減点材料として映りやすいのです。欠点を探そうとしているお客様にとっては、ちょっとした一言も「やはりこの営業は大したことがない」という判断材料になってしまうのです。そのため、こちらから情報や材料を提供すればするほど、お客様の減点に引っかかりやすくなるのです。
では、このような状況で営業はどうするべきでしょうか。重要なのは、粗探しの対象となるような情報を出すのではなく、「今まで様々な取り組みをしてきたにも関わらず、解決されないまま残っている課題」を聞くことです。「今まで様々な取り組みをしてきたにも関わらず、解決されないまま残っている課題」に関する情報をいただければ、「このようにお役に立てます」という提案がしやすくなります。
ここでお客様と営業の間に駆け引きが生じます。営業としては先にお客様の困っていることやお悩みをしっかりと聞きたいところです。一方、お客様からすれば「早くこの時間を終わらせたい」という思いがあるため、悠長なヒアリングに付き合うよりも「まずはあなたの製品やサービスをジャッジするための情報を出してください」という姿勢になりがちです。
効果的な質問で初回訪問を価値提供に繋げよう
そこで有効なアプローチとして、弊社代表の高橋が初回訪問のときに20年以上続けているやり方をご紹介します。
最初に簡単な自己紹介をします。その際、こちらから出す情報は最小限にします。その後、「ところで」と切り出し、お客様に質問を投げかけます。
例えば、業務効率化やDXのためのデジタルサービスを売る営業であれば、次のように聞くのです。
![]()
高橋
御社も既に業務効率化やDXについては、これまでも様々な取り組みをされているのではないかと思います。それでもなお解決されずに残っている課題にはどのようなものがありますか?
「今まで様々な取り組みをしてきたにも関わらず、解決されないまま残っている課題」には、何らかの構造的な問題が潜んでいることが多いです。
これを単純に「御社の課題は何ですか?」というように質問すると、お客様としては早くこの時間を終わらせたいと考えているため、とってつけたような表面的な回答をし、「あなたはこれに対して何か役に立つことができるのですか?」というジャッジする目線になってしまいがちです。
そのため、いかにスムーズに核心部分を聞き出すかが重要になります。「御社も既に業務効率化やDXについては、これまでも様々な取り組みをされているのではないかと思います。それでもなお解決されずに残っている課題にはどのようなものがありますか?」というような聞き方をすると、「実は…」という形で、解決されずに残っている本質的な課題を聞くことができます。
また、別の切り口から質問していく方法もあります。
![]()
高橋
当社のサービスは脇に置いておいて、現在、御社で掲げられている重要方針にはどのようなものがありますか?
お客様が営業の提供できる価値を正確に理解していない場合、目の前の営業が解決できる課題の範囲を非常に狭く捉えていることがあります。このアプローチが効果的な理由はそこにあります。
例えば、「所詮、御社はツール販売の会社でしょう」というように狭く捉えられてしまうと、目の前の営業ができることが極めて限定的に見られてしまい、お客様が自ら話す範囲を限定してしまうことがよくあります。
しかし、「当社のサービスは脇に置いておいて、現在、御社で掲げられている重要方針にはどのようなものがありますか?」という切り口から質問すると、お客様の社内でよく言及されているような本質的な課題について情報をいただけることがあります。
2つのアプローチをまとめると、以下の通りです。
- ①今まで様々な取り組みをしてきたにも関わらず、解決されないまま残っている課題を聞く質問
- ②自社のサービスは一旦脇に置いておいて、お客様の重要方針を聞く質問
これらの質問は、いきなり切り出すと唐突すぎる印象を与えかねませんので、最低限の自己紹介をした上でヒアリングに移行することが重要です。
このアプローチにより、営業が価値提供できるポイントに関する情報を得られやすくなるでしょう。