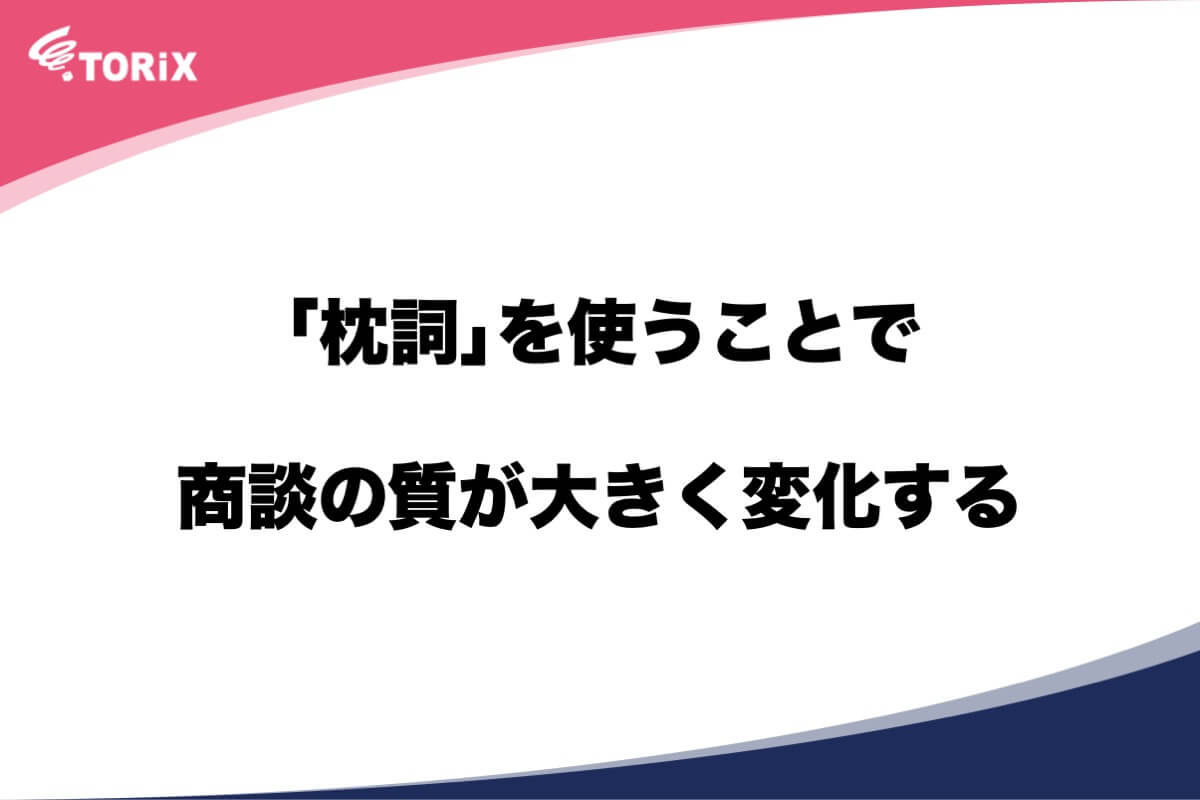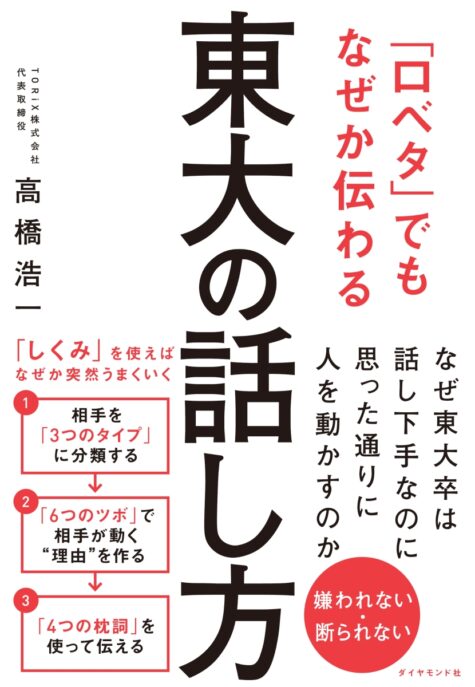受注に直結する「5つの枕詞」
今回は「受注に直結する5つの枕詞」についてお伝えします。
受注に直結する5つの枕詞
- ①「〜とおっしゃっていたので」
- ②「大事なことなので最初に伺いたいのですが」
- ③「個人的なご意見で構いませんので」
- ④「もし仮に導入するとしたら」
- ⑤「最後に1つだけ伺いたいのですが」
それぞれに使うタイミングと理由があります。
商談でヒアリングをする目的は以下の3つに分けられます。
商談でヒアリングをする目的
- (A) お客様の基本的な理解のために必要
- (B) 提案を作るために必要
- (C) 検討意欲や意思決定について知るために必要
よく見られる配分は(A)が10%、(B)が80%、(C)が10%です。しかし、このバランスでは「ズレた提案」や「提案後の停滞」を生み出しやすいです。特に若手の多くは(A)と(C)の比率を増やすことが難しいです。
お客様を理解する質問の重要性は理解していても、「答えるのが面倒くさそうなお客様の表情」や「早く御社の情報を伝えてほしいというオーラ」により、質問をためらってしまうことがあります。
![]()
営業パーソン
こんな当たり前のことを聞いてもいいのかな?いきなりヒアリングしても、答えてくれないだろう…
そこで、先ほど挙げた5つの枕詞が有効です。
①「〜とおっしゃっていたので」
商談の入り口では「お客様が述べた情報」を基に話を進めます。お客様自身の過去の行動や言動が質問のきっかけになります。
![]()
営業パーソン
以前、弊社の担当がお電話でお話させていただいた際、お客様が◯◯と仰っていたと聞いておりますが…
もちろん、お客様の過去の行動や発言を引き合いに出しても、期待よりも反応が鈍いことがあります。しかし、お客様がまだ「品定めモード」の状況でいきなり説明を始めても響きません。
②「大事なことなので最初に伺いたいのですが」
そこで、重要な質問を事前に準備しておくことが大切です。そうすることで、お客様からスムーズに情報を聞くことができます。
特に初対面のお客様に対して、商品の説明を響かせるのは難しいです。しかし、質問であれば「そういうところをちゃんと聞いてくる営業なのね」と短時間で価値訴求をすることができます。商談の前半には以下のような点について理解しておくことが望ましいです。
商談の前半に確認しておくこと
- ずっと解決されずに残っている課題
- やりたくてもできていないこと
- 思うように進まないこと
ヒアリングを進める中で、お客様がどのように発言すべきか迷うことがあります。お客様は関係がまだ築かれていない営業に対しては警戒心を示すことが多いです。
③「個人的なご意見で構いませんので」
そこで、「個人的なご意見で構いませんので」と前置きすることで、お客様の発言のハードルを下げることができます。
①〜③の枕詞を使うことで、お客様に対する基本的な理解を深め、「品定めモード」の状態を解消することができます。その後、簡単な商品説明や提案内容のヒアリングに移ります。その際は商品説明とヒアリングのキャッチボールを意識しましょう。オンライン商談では、一方的に話す時間が長くなりすぎないように注意が必要です。
ヒアリングを終えた後、「それでは、お聞きした内容を基に提案を作成いたします」と言ってすぐに次のステップに進む営業が多いです。しかし、検討意欲や意思決定に関する情報が十分に聞けていない場合、提案がうまくいかないこともあります。
④「もし仮に導入するとしたら」
そこで、次のステップに進む前に「もし仮に導入するとしたら」と前置きし、BANTC情報(予算、決裁者、ニーズ、タイミング、競合)について詳しく聞きましょう。「もし仮に」という言葉を使うことで、お客様の真剣度や温度感を把握しやすくなります。
⑤「最後に1つだけ伺いたいのですが」
BANTC情報を聞いたときに、情報がすぐに得られない場合や、回答を避けられてしまうことがあります。その際、「最後に1つだけ伺いたいのですが」と言って、重要な情報を聞いておきましょう。「最後に1つだけ」という言葉を使うことでお客様はデリケートなことも答えてくれやすくなります。
枕詞で「聞き出せない」を解消しよう
弊社は営業支援を行う会社ですが、その中でも特に即効性があり、インパクトを感じていただけるのが「質問力」をテーマとした研修です。この研修で受講生や参加者から特に反響が大きいのが「枕詞」の使い方についての内容です。
枕詞をうまく使えるようになると、質問への抵抗や恐怖心が大幅に和らぎます。これは質問する側だけでなく、質問される側にとっても同様です。お客様からはぐらかされてしまうことも少なくなり、商談の流れが劇的に変わるほどの効果が期待できます。こうした枕詞の使い方を習得するだけで、商談が大きく改善されます。
弊社代表の高橋がこの枕詞の重要性を意識し始めたのは、今から約20年前です。高橋は営業の世界に入ったばかりの頃、営業職にはオープンで人当たりの良いコミュニケーションが得意な方が多いと感じていました。その一方で、高橋はズケズケと人に質問することが苦手で、どこか劣等感やコンプレックスを抱いていました。
高橋はスムーズに会話できる人がとても羨ましいと感じていました。しかし、商談を重ねるうちに、「聞くのが怖いから」と質問を避けていては大事な情報が手に入らないことに気づいたのです。また、踏み込んで質問をしないと本当に重要なことは教えてもらえないということも少しずつ意識するようになっていきました。
とはいえ、当時の高橋はどうしても「怖い」という気持ちが先に立ち、なかなか質問ができませんでした。そんな中、恐る恐る枕詞を使い始めたところ、思いもしなかった効果があったのです。
高橋は特に印象に残っている場面があると言います。それは、大企業のお客様への営業の際に本音をなかなか話してもらえないと感じた場面です。そこで、高橋が「個人的なご意見で構いませんので…」と前置きして質問をしてみたところ、意外にもお客様が色々と話してくれたのです。この経験を通して、「聞き方次第で相手の反応が変わる」ということを20代の高橋は非常に強く実感したのです。
それから高橋はA4サイズのノートを使い、その中央に縦線を引いてページを左右に分け、左側には「聞きたいけれど、なかなか聞けないこと」や「聞いたが、教えてもらえなかったこと」を書き、右側には「どういう聞き方をすれば聞き出せるか」を書き込んでいきました。そして、ある程度聞けないことが減ってきたと感じたら、その項目に横線を引いて消していく、という方法を取りました。
この作業を繰り返していくうちに、初めは個別に考えていたことが次第に体系化され、「枕詞を一言添えるだけで、多くの『聞き出せない』という問題が解決できるのだ」と実感するようになりました。そして応用も利くようになり、「枕詞の使い方さえ習得すれば、ほとんどのことは聞くことができる」という確信を持つようになったのです。
お客様の「認知的不協和」を解消しよう
これには「認知的不協和」という心理学のコンセプトが関係しています。高橋はよく書籍でも「認知的不協和」について解説していますが、これは「人は矛盾する認識があるとモヤモヤする」という心理です。たとえば、営業からデリケートな質問を受けたお客様は、「答えた方がいいのかな、答えない方がいいのかな」とモヤモヤを感じます。そのため、「まずははぐらかして様子を見てみよう」といった反応を示すことが多いのです。
では、なぜこのような現象が起こるのかというと、人は何かと何かの選択に迷った際、自分の選択を正当化することで心の安定を図ろうとする傾向があるからです。
お客様が情報を教えてくれないのは「教えない正当性」があるからです。逆に、この認知的不協和を逆手に取れば、営業に情報を提供することに正当性があるとお客様が納得した場合、むしろ積極的に教えてもらえるようになります。
先ほど挙げた「個人的なご意見で構いませんので」という表現ですが、これはお客様に「今から教えていただくことは会社の公式見解として扱うわけではなく、あくまでカジュアルに、あなた個人の意見として伺います」というニュアンスを伝えるための1つの「落としどころ」です。そうすることで、お客様も「教えるべきか、どうしようか」と迷ったときに、「個人的な意見としてなら答えてもいいか」と思って話してくださるのです。
また、人は迷っている状態を放置するのは気持ち良くないため、その状態を解消しようとします。例えば、営業が「御社には今回特別にお安くします」と特別値引きでクロージングをかける場面も同様です。お客様が「購入するか、しないかで迷っている」場合、営業としては迷ったままで決めてもらえないのは困るわけです。そこで「落としどころ」として特別値引きをすることで、お客様の決断を促そうとするのです。これもまた、認知的不協和を解消し、適切な「落としどころ」を提示する一例と言えます。
重要なのは、「答えることへの落としどころを先に作ってから質問すること」です。例えば、「正確な見積もりを作成するために伺いたいのですが」という一言を添えることで、予算を曖昧にしていたお客様が具体的に予算を教えてくれることがあります。また、「御社にとって最適な提案をしたいので伺いたいのですが」と言えば、競合他社の名前を教えてもらえるケースもあります。
重要なのは「お客様が答えない理由」を減らすこと
高橋の著書『「口ベタ」でもなぜか伝わる 東大の話し方』(ダイヤモンド社)の中で「ノー・キャンセリング」という枕詞について解説しています。
「ノー・キャンセリング」とは「相手が断りそうな理由をこちらから先に提示して解消してしまう」という手法です。
例えば、「差し障りのない範囲で構いませんので」というのは典型的なノー・キャンセリングの枕詞です。お客様は「これを話してもいいのか、どうしようか」と迷う場合、「話すことに差し障りがあるのではないか?」と思っています。「差し障りのない範囲で構いませんので」という枕詞にはその迷いを先に解消するという働きがあります。
例えば、お客様が「会社の課題や悩みを外部の企業に話して良いのか?」と悩むことがあります。こうした懸念がある場合、お客様はつい話をはぐらかしたり、隠したりする傾向にあります。しかし、ノー・キャンセリングでは、そうした断りが予想されるなら、こちらから先にそれを解消してしまうのです。「個人的なご意見で構いませんので」といった枕詞も、ノー・キャンセリングの一例です。
このように先にお客様の迷いを解消しておくことで、「お客様が答えない理由」が減っていきます。お客様をより深く理解し、お客様のためになる提案ができるように、ぜひ積極的に活用してみてください。