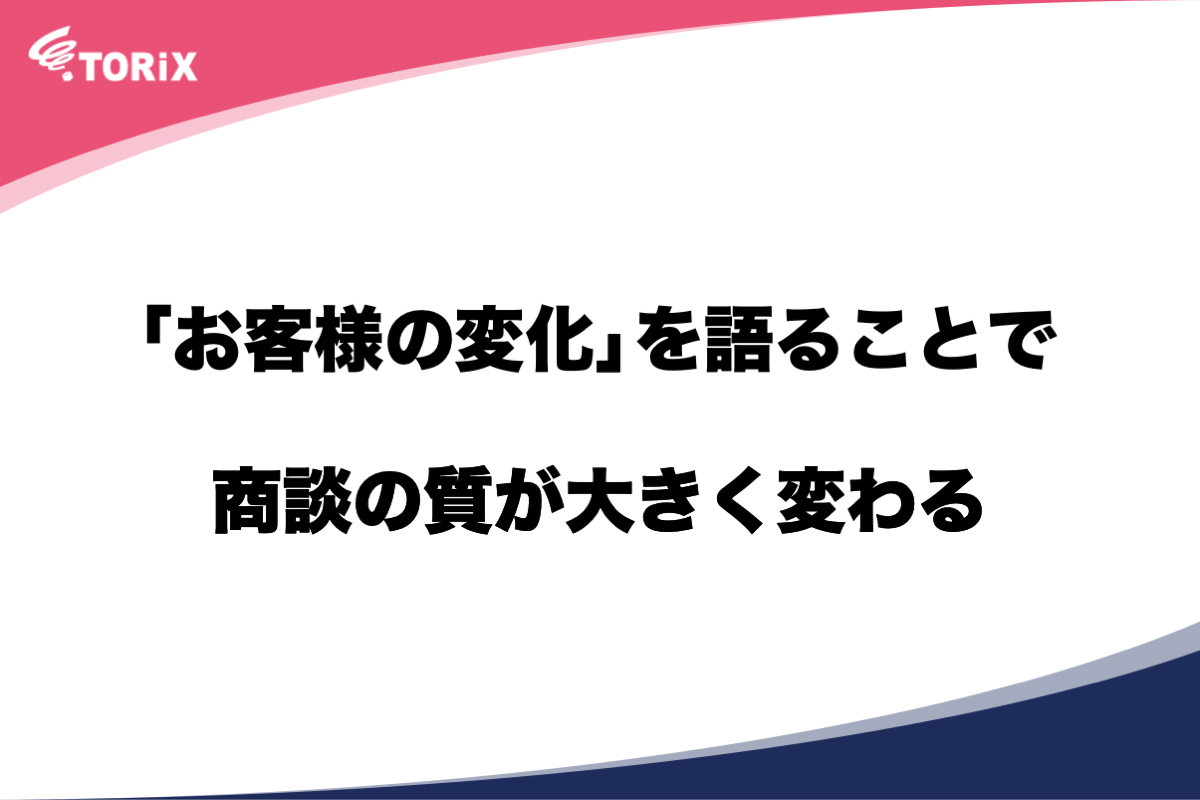重要なのは「お客様の変化」を語れること
営業の「引き出しの多さや深さ」は重要です。 商談ではお客様が深くうなづき、思わずメモを取るような話をどのぐらいできるかが求められます。 これは「商品知識や業界知識の詰め込み」「立て板に水の如くの滑らかトーク」だけでは足りないので、コツをつかむ必要があります。カギとなるのは「お客様の変化」を語れることです。
「お客様の変化」とは「こういう状態だったお客様が、(自社の商品・サービスを利用いただくことにより)こんな状態になる」ということです。Before→Afterで「お客様の変化」にどのぐらい現実味を持たせられるかが重要です。まず、前提としてお客様のことを理解し、「Beforeの状態」への解像度を上げる必要があります。
「深くうなづき、メモをとる意味がある」と思われる要素は「お客様の変化」に関係しています。
- 今まで自分/自社が行き詰まっていた原因がわかった(これを取り除けば良い未来がある)
- 自分/自社が具体的にどうすればいいかのヒントがあった(だからメモをしておき、後で具体的なアクションにつなげたい)
一方で、大量の商品知識や業界知識に関する情報は「資料に書いていないからメモしておくか」ということはあっても、お客様にとって「変化」につながらなければ、深いうなづきは生まれません。 また、立て板に水の滑らかトークも「お客様の変化」に関係していなければ聞き流されてしまいます。
提案する商品やサービスはお客様の「変化」につながるものであるはずです。そのため、商談では「何が変わるのか」「どう変わるのか」「なぜ変わるのか」にひもづけて語る必要があります。 同時に、「お客様は他の手段ではなぜ変われないのか」ということにも通じていなければなりません。それはお客様にとって積年の課題です。
自社商品は「手段」として考えよう
ここで、営業が「お客様の変化」に実際に立ち会ってきた経験値が物を言います。数々の変化を支援してきたからこそ、重みのある言葉で語れるのです。 一方、「経験値」で話を片付けてしまうと、「じゃあ、入社したばかりの営業はどうしたらいいのか?」となります。 そこで必要になるのは「自社商品の手段化」と「受け売り力」です。
以前、弊社代表の高橋が中途入社して間もないのに実績をあげているハイパフォーマー営業に話を聞きました。「なぜ前職と全く違う業界・商品で、そんなに売れるんですか?」と聞いたら、「私が提供しているのは、ただの『手段』です。お客様の成功が目的なので、前職とやっていることは同じです」という答えが返ってきました。
多くの営業は自社の商品・サービスを主役として説明し、「お客様が買うかどうかご判断ください」という世界観でいます。 この主従を逆転させ、「お客様にどのような変化を起こすのか、それに自社商品がどう貢献するのか」を語ると、お客様は「変化」の部分に反応し、結果として耳を傾けてくれます。
「お客様の変化が目的、自社商品は手段」と捉えられるようになると、話を構造化する力が上がります。「AからBへの変化を実現する。そこには自社商品がこのように貢献できる」という図式で話すことができると、社内にある事例を上手く説明できるようになります。それが「受け売り力」が向上するということです。
こうして「お客様の変化に役立つ話」のネタが蓄積され、伝えるスキルが磨かれていきます。お客様は「変化」が実現できそうな気配を感じると、うなづきやメモが増えます。それはポジティブな反応です。「話す→ポジティブな反応」というフィードバックを沢山経験することでコツがつかめ、引き出しが徐々に増えていきます。
「お客様の成功」に意識を向けよう
弊社は研修や講義、ワークショップなどを設計する際、まず最初に考えるのは「参加者が終了後にどんな状態になっているべきか」というゴールです。ゴールが定まったら、次に現在の参加者の状態を考えます。現在地とゴールをつなぐ手段が研修プログラムです。
本を書くときも同じです。読者が読み終えた後にどうなってほしいか(ゴール)、またどのような読者に向けて書くのか(現在地)、その差分を埋める手段が本です。
つまり、現在地からゴールに向かって変化を促すことが仕事の根幹にあるのです。
営業においては、お客様が求める変化と自社商品を結びつけることができれば成果につながります。しかし、そこに慣れるまでは、お客様の変化を考えるだけでは自社商品と結びつかないことが多いです。
「自社の商品が売れなくてもお客様が幸せになればそれでいい」といった話もよく聞きますが、営業としてはやはり自社商品を選んでもらいたいという思いがあるはずです。そのため、お客様の変化と自社商品をどのように結びつけるかが重要です。
最も大事なのはお客様を成功させること、幸せにすることです。それに集中していれば現状とゴール、そしてその手段としての商品も自然に言葉で表現できるようになります。お客様の成功や幸せを実現することに全力を注げば、自然と自分の提案する商品も売れていきます。
「ギブすること」に成功の本質がある
そうすると、「いや、そうは言っても、そもそも自社の商品を買ってもらわなければ、お客様を成功させることはできない」と考える方もいるでしょう。これはその通りです。自社の商品を買っていただかないままで、お客様を成功に導くのは困難です。
ここで大事なのは、お客様かどうかは一旦置いておいて、まずは「一人の人間として、周囲の人々を成功させる」ということです。その延長線上に、自然とお客様の成功があります。
よく「ギブアンドテイク」の話で、「成功する人はギバーである」と言われます。「ギバー」が集まる場所では皆が親切で、惜しみなく与え合う姿が見られます。そうした場では「人から何かをもらおう」という雰囲気の人がおらず、皆が自然にギブをしています。そういう人は世間でも成功を収めており、その姿勢にこそ成功の本質があります。
周囲の人たちに成功してもらう、幸せになってもらうことを目指す際の最大の障壁は「見返りを求める時間軸」です。人に何かを与えた時、どうしてもその見返りがほしくなるものです。
弊社代表の高橋は25歳で最初に起業したときには数百万円の借金をし、新卒の初任給よりも低い役員報酬で働いていました。お金がない時代をリアルに体験したわけです。
しかし、高橋がその時に感じたのは「見返りを早く求めると、上手くいかない」ということでした。高橋がなぜそう感じたのかというと、当時、多くの成功者から同じような話を聞いていたからです。最初はそれが「きれいごと」のように思えたようですが、それでも信じてやってみようと決め、その姿勢を貫くうちにいつの間にか売上に困らなくなっていったのです。
お客様に「具体的な変化」をもたらそう
他人を成功させる人は、決して軽んじられることはありません。よく考えてみると、これは当然のことです。「この人と一緒にいると上手くいく」「幸せになれる」という人がいたら、その人を軽んじることはありません。
つまり、周りの人に何らかの価値を提供してその人が成功したり、幸せになったりするような変化をもたらすことができれば、相手から軽んじられることはないのです。逆に、もし周囲の人を成功に導いているのに軽んじられるのであれば、そのコミュニティからは離れるべきです。
世の中には善意に満ちた人々が集まるコミュニティや組織がたくさんあります。善意に基づいた行動を続けていれば、自然とそういったコミュニティに迎えられるでしょう。
ここで注意すべきことは、単に自分が「良いことをしているつもり」になっているだけで、本当の意味で相手に成功をもたらしていないことがあるということです。
良いことをしているつもりであることと、実際にリアルな成果をもたらしていることには厳密な線引きが必要です。実際に相手に具体的な変化が起こっているのであれば、それは成功させていると言えます。
「お客様の変化」はまさにこうした成功体験を何度も積み重ねてこそ、リアルで生々しい言葉で語れるようになります。