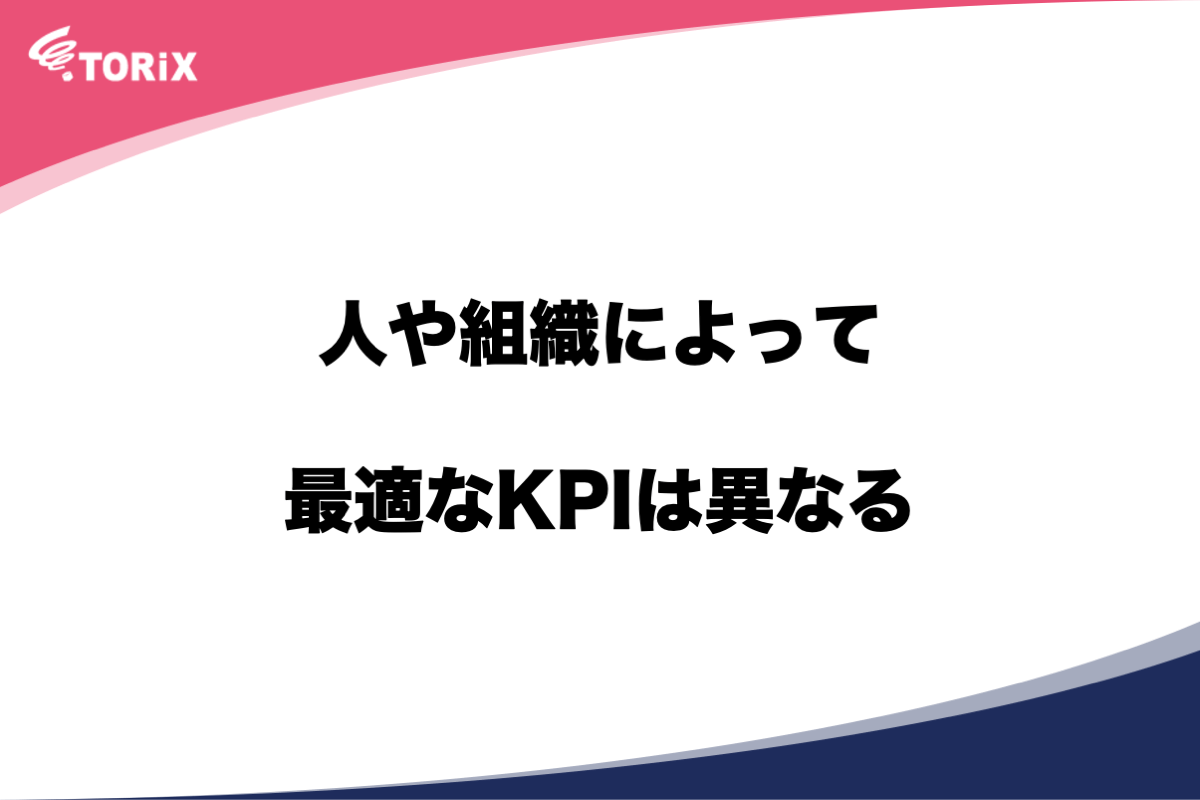KPIを設定する際のカギは「再現性」
よく「売上アップに繋がるKPIは?」と考える人がいますが、ここから考え始めると落とし穴にはまりやすいです。なぜなら、「売上アップに繋がる」だと選択肢が多すぎて正解・不正解がわからないからです。
そこでおすすめするのは「再現性高く成果を上げる行動習慣が正しく身につくKPIはなにか?」について考えることです。
例をあげて解説します。
仮に「月に20件のお客様訪問」をKPIにするとどうなるでしょうか。
もちろん、訪問件数が多くなることが売上アップに繋がることは否定できません。そのためKPIとしては一見、悪くないように思えます。
ただ、これはどういう行動習慣を誘発するでしょうか。
![]()
営業パーソン
月に20件のお客様訪問をしないと怒られるから、会ってもらいやすいお客様のところに行こう…
![]()
営業パーソン
今月の訪問目標をクリアしないと…とりあえず何でもいいからアポイントを取ろう…
こうなると「ニーズや予算の有無よりも、会ってもらいやすいかどうかでお客様を探す」「大事な月末に訪問件数のことばかり考える」という習慣が身についてしまいます。
「行動習慣」を変えるKPIを設定しよう
もし仮に「訪問件数」をKPIに置きたいなら、以下のように工夫すると良いでしょう。
- 会うべき部署や役職を絞り込み、例えば「50万円以上の決裁権を持つ人物への訪問件数」などにする
- 1ヶ月ではなく1週間あたりにするなど、「月末にまとめてノルマをクリア」をやりづらくする
- 「今の受注額が低すぎる人」「スキルが低い新人」など、対象の人物や期間を限定する
訪問件数はわかりやすいのでよく使われているKPIですが、注意が必要です。
代わりに、例えば弊社では「フェーズAからフェーズBにアップした●●万円以上の商談件数(1週間あたり)」といったものを新規営業チームのKPIに置いています。
これによって以下のように「行動習慣」が良くなります。
- 単に訪問しても評価されないので、お客様の合意を得て商談を前進させることを意識するようになる
- 1ヶ月あたりではなく1週間単位なので、「まとめて何とかする」が通用せず、「コツコツと継続的に仕込みをしておく」ことを自然とするようになる
- 「どんなお客様でもいいのでアプローチする」のではなく、「将来的に一定金額の案件になりそうかどうか」を考えながらアプローチ先を選ぶようになる
もちろん、弊社のKPIが唯一の正解というわけではなく、企業のステージや商材、ビジネスモデルによってKPIは変わってきます。
ここまでをまとめると、以下の点について意識することが重要です。
- 「売上アップに繋がるKPIは?」と考えても正解にたどり着くのは難しい
- 「再現性高く成果を上げる行動習慣が正しく身につくKPIはなにか?」で考える
KPIの「賞味期限」を意識しよう
より詳しく解説します。
KPIの設定は多くの経営者やマネジャーからよく相談される難しいテーマの1つです。なぜなら商材やビジネスモデル、企業の成長ステージによって、適切なKPIは異なってくるからです。したがって、「このKPIさえ設定していれば成功する」といった絶対的なものを提示することはできません。
KPIには「賞味期限」があります。賞味期限とは、食べ物のように時間が経つと価値が失われたり、場合によっては弊害が生じることを指します。KPIにもこれと似た性質があるのです。
再び「訪問件数」をKPIに設定することを考えてみましょう。訪問件数をKPIにすること自体が間違いというわけではなく、時期や組織によっては有効です。しかし、「訪問件数」というKPIは一時的には成果を上げても、長期的には「部分最適」の問題を引き起こしやすくなります。
どういうことかというと、「訪問件数」をKPIにした場合、訪問件数は増加する一方で、「次に繋がる成果」が生まれなくなることがあるのです。先ほども述べたように、訪問件数を重視するあまり「訪問しやすい場所」にばかり足を運ぶようになり、本来の営業活動の目的から外れてしまうのです。
KPIは時間が経つと部分最適を引き起こす性質があるという認識が重要です。そして、KPIの「良し悪し」を判断する際には「賞味期限」が短すぎないかがポイントになります。賞味期限が短いKPIはすぐに効果を失うため適切ではありません。一方、賞味期限が長く、集中して取り組んでも持続的に良い効果を生むKPIが優れたKPIと言えます。
賞味期限が長いKPIとは「成果に繋がる再現性のある行動習慣」を促進するものです。そのKPIに向かって行動することで部分最適が起きても問題は生じず、むしろ良い結果がもたらされるようなKPIです。それは正しい行動習慣が身に付き、持続可能な成果を上げるために設計されたKPIです。
人や組織によって最適なKPIは異なる
ただ、仮にそのようなKPIを設定したとしても、人によってはその成長ステージを早く乗り越えてさらに先へ進むケースもあるでしょうし、会社のビジネスが順調に進むと単に案件数を増やすだけではなく、「単価を上げる」といった新たな課題が出てくることもあります。こういった場合、KPIを再度見直す必要が生じるのです。
例えば、KPIの達成は良いが、最終的な成果(売上目標の達成率)が良くない人がいるとします。また、その逆にKPIは達成できていないけれども、売上目標は達成している人もいるでしょう。こうなると、そのKPIはあまり機能していないと考えられます。
訪問件数を例に挙げると、既存のお客様で十分な売上を確保できている営業は、訪問件数が少なくても売上を上げられることがあります。その場合、その人の売上目標達成率は高くても、訪問件数というKPIには達していません。
つまり、その人にとっては訪問件数をKPIとすることの「賞味期限」が切れているわけです。こうした状況が組織内で多く見られるようになれば、KPIを見直す時期が来ているのではないかと考えられます。
重要なのは「賞味期限が長いKPI」を設定すること
KPIの定め方は野球の打率に例えると分かりやすいかもしれません。打率というKPIを設定すると、打率を維持するために打席に立たないという選択肢も考えられます。例えば、シーズン終盤で首位打者の選手が「これ以上試合に出ると打率が下がるかもしれない」と考えて試合に出ないという選択をするかもしれません。
KPIを分母と分子で考える場合、特に気をつける必要があります。パーセンテージで表せる指標は一時的に状況を確認するには便利ですが、長期的に使用すると予期しない結果を招くことがあります。
例えば、弊社では受注率は参考指標としては見ていますが、重点KPIには設定していません。なぜなら、受注率を重点KPIにすると受注率が下がることを恐れてチャレンジ提案が減少する可能性があるからです。
賞味期限が長いKPIを設定することが大切です。賞味期限が長いKPIとは横軸にKPI、縦軸に業績を置いた際に両者がしっかりと相関するものです。
もし最初に設定したKPIが完全に正しいものでなければ、必要に応じて調整しましょう。組織には「一旦このKPIを見てみますが、これは仮のものなので状況に応じて変更します」と伝えることが大切です。
不適切なKPIが組織全体に浸透し、結果的におかしな方向に進んでしまうことを防ぐためにも、KPIは「賞味期限」を意識しながら設定しましょう。