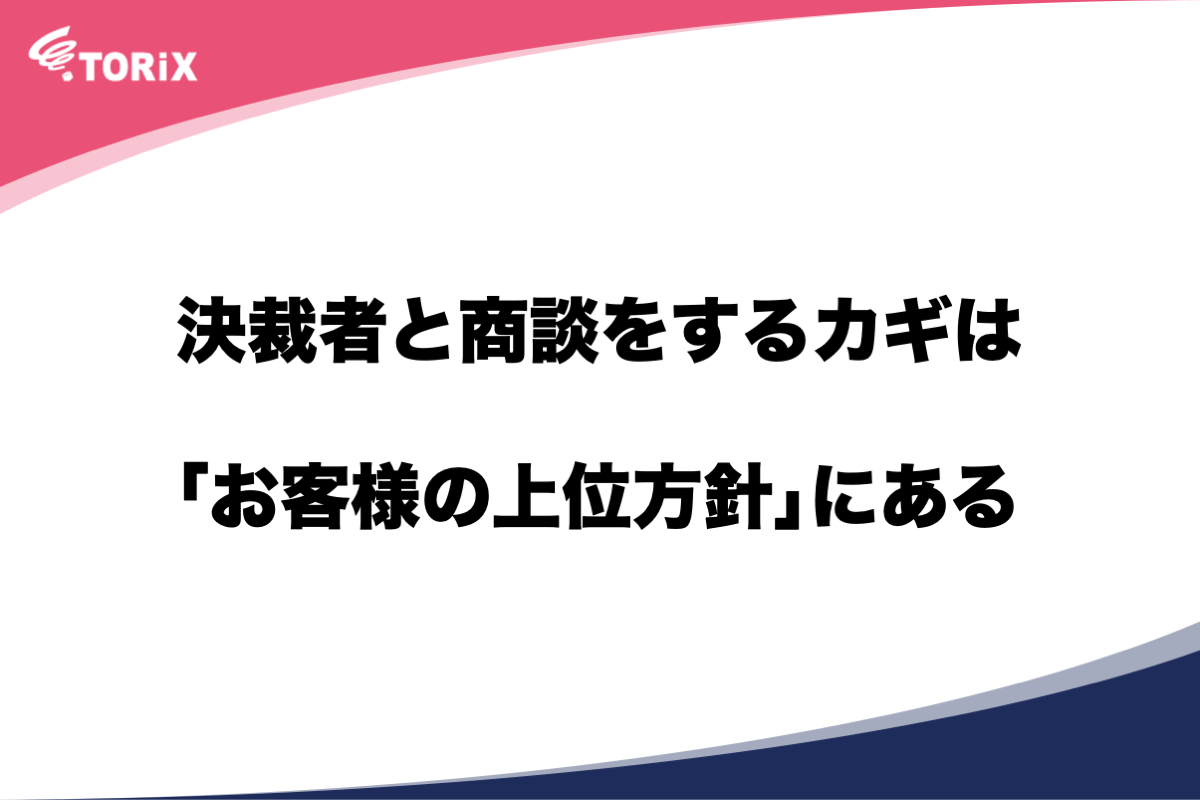「決裁者商談に繋がらない壁」の乗り越え方
今回は「決裁者商談に繋がらない壁」の乗り越え方についてお伝えします。
以下は「決裁者商談にたどり着けない営業のための8つのチェックポイント」です。
1
カウンターパートの分析
カウンターパート(目の前のお客様)が決裁者に対して一定の影響力を持ち、然るべき力(あるいはポジション)を有する方であるかを見極めることが重要です。名刺上の肩書よりも、「会社の課題」に対して自分なりの考えを持っている実力者であることが重要です。
2
カウンターパートの引きつけ
カウンターパートを味方にする前に「私も上司を同席させますので…」と切り出してしまうと、社内調整を頑張っていただけません。あるいは、「決裁者に会わせていただけますか?」という打診が早すぎると、カウンターパートにご本人を軽んじていると思われてしまうことがあります。
3
「決まらないストレス」の把握
決裁者に繋がっているカウンターパートが「決裁者に決めてもらえなくてヤキモキしている」論点を探します。「これさえ決めてもらえたら仕事がやりやすいのに」というカウンターパートのストレスをつかんだら、協働しやすくなります。そうすれば社内調整も頑張っていただきやすくなります。
4
論点の拡張
論点が同じ大きさのまま決裁者の同席を試みると、カウンターパートが「きちんと仕事をしていない(力不足で上が出ざるを得ない)」ように映ってしまいます。「当初は営業効率化ツールを検討していましたが、マーケティング領域にも関わる話になったので…」といったように、「決裁者が出る理由」が大切です。
5
「他の関心事」の把握
決裁者が他のことに関心が強い場合、その関心事と無関係のように映るとアポイントメントの優先順位が下がってしまいます。そこで、「本件に関係なくても構いませんので」と前置きし、カウンターパートから決裁者の最近の関心事を網羅的に聞き、アポイントメントの趣旨との結びつけを図りましょう。
6
過去の同席基準の確認
権限移譲については様々なスタイルや好みがあります。そこで、その決裁者は過去どのようなときに現場に降りてきて議論に加わり、どのようなときは権限を移譲してメンバーに任せたままにしたのかを確認しましょう。その同席基準に関する過去の事実を聞いておき、今回は「同席に値するアポイントメント」であるというロジックを固めましょう。
7
当日のキャンセル対策
アジェンダは事前に送っておくのが望ましいです。アジェンダが不明確だと、決裁者が「あれ、これは何を話す場なの?」とカウンターパートに質問することになりますが、その展開になると「じゃあ、任せるね」となりやすいです。事前に「決裁者が関与する意味がある」と感じられるアジェンダを送っておきましょう。
8
核心質問の準備
アポイントメントの趣旨が「決裁者への説明」に留まっていると、「これだったら最後までいなくてもいいな」と思われ、途中で退席されてしまう可能性があります。冒頭の数分で、決裁者が前のめりになるような質問をすることができるように準備をしておくことが重要です。
「お客様の上位方針」を中心に話をしよう
多くの営業がよく「私も上司を連れてきますので、○○様も上司の方を連れてきていただけませんか?」と言いますが、弊社はそのようなアプローチはあまりおすすめしません。相手方の決裁者の立場に立つと、突然、部下から「営業を受けていて、先方の会社の上司も同席するので、次回の打ち合わせに参加いただけませんか?」と言われても、モチベーションは全く上がらないからです。
また、お客様から「上司を連れてきますので、説明していただけませんか?」と言われるケースもありますが、基本的には、決裁者のようにある程度の役職に就いている方は人から説得されることを好みません。一から説明を受けて素直に納得するようなタイプの方は非常に少ないです。組織の上位役職者になればなるほど、ご自身の意見をお持ちで簡単には説得されない方の方が多くなります。
そのため、最初から「説得」という文脈で場を設定してしまうと、うまくいかないのです。
そこで、以下の言い回しがおすすめです。
![]()
高橋
当社のサービスのことは一旦脇に置いておいて、今、御社ではどういうことが上位方針として出ているのでしょうか?
「まだ購入について本格的に検討できる段階ではない」「担当者は承諾していても決裁者はよく知らない」という場合、決裁者にとって外部の商品やサービスを購入するという話は「突然きたトピック」です。ある意味で「横槍を入れられた」というふうに感じられてしまうこともあります。「当社のサービス」ということを中心にスタートすると、どうしても説得めいた文脈にならざるを得ないのです。
そこで、まずは枕詞として「当社のサービスのことは一旦脇に置いておいて」という前置きが必要になります。先ほどお伝えしたように、決裁者は説得されることを好まない傾向にあります。自分が意図しない文脈で話を持ちかけられることは、決裁者にとって心地良いものではありません。
本来、役員から出されているビジョンや戦略、方針があって、その文脈の中で「このサービスが必要だ」という話をすることが自然な流れです。そのため、まずはそれをしっかりと聞き取ることが大切です。
重要なのは上位方針と現状の繋がり
ただし、お客様としては、ある商品を扱う営業が目の前にいれば、商談ではその商品の話をするのだと考えるものです。
例えば、オフィス機器のレンタルをする会社の営業の場合を考えてみます。相手が企業の総務担当で、営業としてはオフィス機器のレンタルの話に繋げたいとします。しかし、総務担当の方は年中オフィス機器の調達方法について考えているわけではありません。それでも、オフィス機器のレンタルをする会社の営業が目の前にいれば、「オフィス機器をどうするかについて話をするのだろう」と想像します。
そのため、突然ビジョンや戦略、方針の話を出されると文脈が合わないのです。そこで、「当社のサービスのことは一旦脇に置いておいて」という枕詞が重要になります。それにより、その会社の総務部の役員がどんなメッセージを出しているのかを聞くことができます。
そうすると、例えば「ワークスタイルはこうあるべき」「こんな会社にしていく」といったビジョンや戦略、方針を聞くことができます。そして、それを具体的に実現するための目標が組織の中に下りてきています。まずはそれを正確に把握することが必要です。
しかし、総務担当の方からすると、目の前にオフィス機器のレンタルをする会社の営業がいれば、まずは「うちはこれを必要としているかどうか」という文脈で考えるはずです。そうすると、いきなり営業から「御社の方針は何ですか?」と聞かれても、お客様は「特にオフィス機器についてはありません」と答えざるを得ません。
だからこそ、「当社のサービスのことは一旦脇に置いておいて」という枕詞をつける必要があるのです。そうすることで、お客様は「ああ、商品の話とは関係なくですね」となり、上位方針として出ている話を聞くことができるのです。
そして、そこで上位方針の話が出てきたら、それを深掘りするのです。例えば、総務部の役員の方が「ワークスタイルの変革」ということを掲げており、総務担当の方はその文脈の中で「社員の仕事環境を整える」という役割を担っているとします。
そうしたら、次は現状を「上位方針の要望を満たせているポイント」と「上位方針の要望を満たせていないポイント」に分解して聞いていきます。
そうすると、上位方針に対して100点満点で応えられているわけではない場合、どこかしら課題を抱えていることになります。
このように丁寧に掘り下げていくと、何かしら提案できる余地が見えてきます。
「論点のスケール」を発展させよう
ここまでの内容を整理すると、決裁者商談までの流れは以下の通りです。
決裁者商談までの流れ
- ①上位方針を確認する
- ②それに沿って目の前のお客様が現在どのようなミッションを遂行しようとしているのかを確認する
- ③その中でどのような課題があるのかを確認する
そして、出てきた課題を掘り下げていくことで、それが上位方針に繋がっていることを再確認するのです。例えば、総務担当の方が仕事環境を整えるためにオフィス機器のレンタルを検討していたところ、実はそれはオフィス機器のレンタルにとどまらず、「ワークスタイルの変革」というより大きな課題に取り組もうとしていた、といったようにです。
そこで、「このような大きな課題についてのご判断をいただきたいので、今度の打ち合わせに決裁者の方に来ていただけませんか?」という流れで話をします。これが先ほどお伝えした「④論点の拡張」というもので、現場の担当者が扱える論点から、よりスケールの大きな論点に話を発展させていくのです。
ただし、これは商材ありきの「この商品を買ってくれませんか」という話からの展開ではありません。あくまでも「上位方針を実現しようとする中で出てきた課題をよく掘り下げてみたら、大きな話だった」という流れです。もし話が総務担当レベルの論点のままであれば、決裁者が出てくる必要はありません。
だからこそ、決裁者に出てきてもらうには論点を広げることが必要です。また、その際に決裁者にどのような判断をしてもらいたいのかを具体的に設定できれば、決裁者が出てくる理由が明確になります。
今回お伝えした内容をもとに、「決裁者商談に繋がらない壁」を乗り越えましょう。