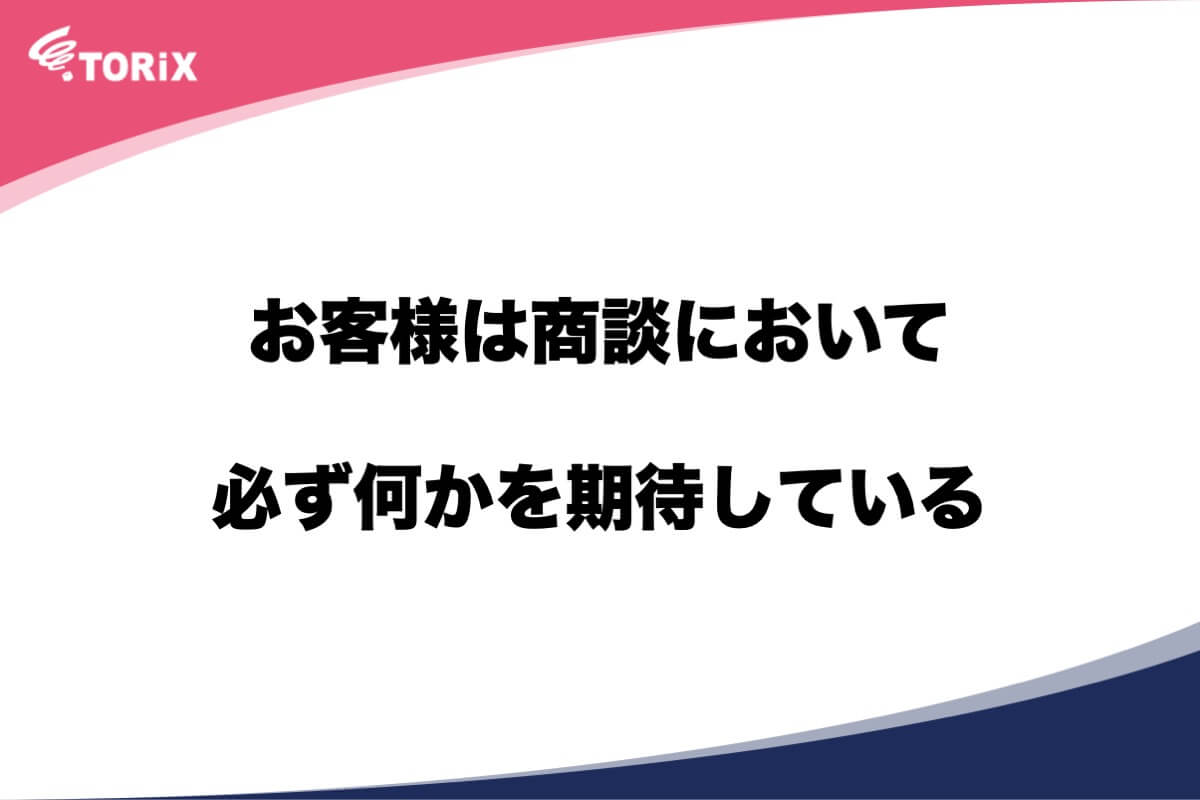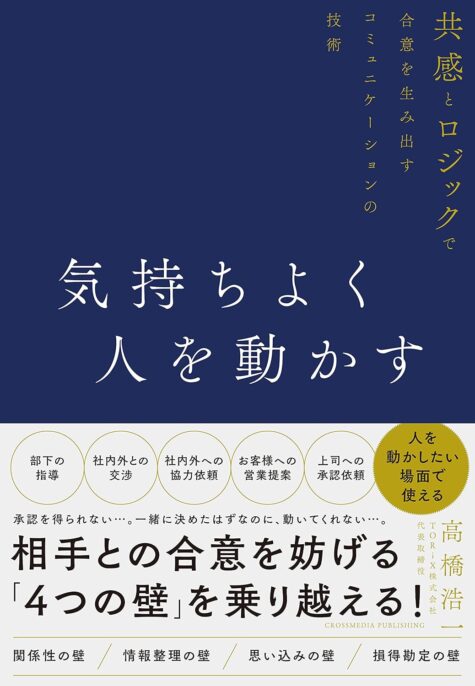お客様の「不」に意識を向けよう
「お客様に興味を持てない」という悩みは、多くの営業やその上司が抱える共通の問題です。
- 「お客様に興味を持てないので営業には向いていない」(本人の悩み)
- 「最近の若手はお客様に興味を持たないから距離を縮められない」(上司の懸念)
これらの問題を解消するには、視点を変えて「お客様の『不』を理解すること」に意識を向けることが重要です。
「外向型」「内向型」という概念はよく知られています。弊社代表の高橋は心理テストを受けると、90〜95%の割合で内向型という結果が出ます。高橋は人との接触が苦手で、対人恐怖症の時期が10年以上も続きました。他人に興味を持ちにくい自分に劣等感を抱き、友人や知人が楽しそうに明るく会話をする様子を羨ましく感じていました。
高橋は16歳で飛び込み営業のアルバイトを経験し、人と話すことは多少は慣れましたが、今でも得意ではありません。講演の聴講者と1対1でお会いすると、「高橋さん、今日は体調が悪いですか?おとなしいですね」と聞かれることがあります。しかし、高橋は内心「これがいつもの私なのです…」と感じているのです。
高橋が幸運だったのは、25歳で起業し、死に物狂いで営業に挑む必要に迫られた時でした。営業の基礎を教わる機会がなかったため、試行錯誤の連続でした。既存の営業本を読んでも実行に移せない自分に落胆していたとき、ある記事が目に留まりました。
それは、「ビジネスを通じて社会の『不』を解消する」という記事でした。不便、不満、不安といった『不』に注目するという考え方は、当時の高橋にとって衝撃的でした。高橋は、「お客様との商談でも、とにかく『不』に焦点を当てたらどうなるだろうか」と思いました。
それまで高橋は、「お客様と良好な関係を築かなければならない」「お客様との距離を縮めるべきだ」という強迫観念に囚われていました。しかし、それらの思い込みを手放し、自社の商品を売ることすらも忘れ、とにかくお客様の「不」を理解することに注力しました。すると、商談における会話の焦点が自然と変わるようになったのです。
お客様の「不」を整理することが受注に繋がる
当時の高橋は「アイスブレイク→会社紹介→ニーズヒアリング→提案→クロージング」という流れを忠実に遂行することに一生懸命でした。しかしある時、一旦それを捨てて「まずはお客様がどのような『不』を感じているのか、そこだけにしっかりと向き合おう」と考え直しました。結果として提案のきっかけが見つからず、ただ話を聞いただけで終わった商談も少なくありませんでした。
そんな中、あるお客様から聞いた「不満」が高橋にとって大きな転機となりました。
![]()
お客様
いや〜、いろいろと話を聞いてもらったのに、提案依頼もできずすみませんね。でも、ほとんどの会社は自社の商品を押し込んでくるばかりで…。逆に今日の商談はありがたかったです。
高橋は驚きました。提案すらしていないのに、感謝されていたからです。
そこで高橋は思わず、「どの部分がありがたいと感じたのか」を深掘りしました。すると、次のような答えが返ってきました。
![]()
お客様
悩みや課題を社内で話すと「愚痴を言わずに何とかしろ」と言われるし、社内には良い相談相手もいないので、考えがまとまらないことが多いのです。今日は、頭の中が整理できて助かりました。
悩みや愚痴を聞き、それを一緒に整理するだけで感謝されるというのは、当時の高橋にとって新しい発見でした。そこからしばらく「売ることを意識せず、お客様の『不』をただひたすら聞いて整理する」ことに徹した結果、自然と受注に結びついた案件も生まれました。
「お客様に興味を持てるかどうか」という観点で捉えると、苦手意識を持つ人もいるでしょう。しかし、「お客様の『不』を理解する」ことに意識を向ければ、それは技術で磨けるものになります。努力次第でいくらでも上達が可能になるのです。
商談でお客様は必ず「何かを期待している」
もし仮にお客様が本当に何も困っていないのであれば、「助けてくれるであろうような相手」とわざわざ時間を設けることはありません。お客様は何かしら困っていることや満たされていない部分があるからこそ、社外の営業と会っているのです。お客様は営業との話を通じて何かしらのヒントや良い情報を得たいと期待しています。時間を割いて会う以上、少なくともそういった期待はあるに違いありません。
たとえしつこい売り込みの電話で仕方なく会うことになったとしても、例えば30分という時間を使うのであれば、自分が抱える問題について何か有益な情報を持ち帰りたい、というささやかな期待はあるはずです。
若手の営業と話をすると、商談の時間配分の際に「最低限こちらのことを伝えなければならない」と考える方が非常に多いです。しかし、例えば30分のアポイントがあった場合、用意した資料を説明するのに20分かかるとしたら、お客様からの質問を受けたり、ディスカッションをしたりする時間は10分しかありません。それだとお客様との関係構築が十分にできないことがあります。
高橋の著書『気持ちよく人を動かす』(クロスメディア・パブリッシング)にもありますが、商談は時間配分が非常に大切です。具体的には、自分が何かを伝える時間を全体の2割程度に抑え、残りの8割はお客様とのインタラクティブなやり取りに使うのが良いでしょう。
では、その2割の時間で何を話すか、そして残りの8割の時間で何をすべきかですが、まず2割の部分では最低限の自己紹介と、残りの8割の時間に繋がるようなフックとなるキーワードを伝えることが重要です。
「フックとなるキーワードを伝える」というのは、具体的には「ここについて質問してもらえたらいいな」と思う材料を提示することです。これは、採用面接にも似ています。多くの会社から求められる人材は一方的に話すだけではなく、履歴書や職務経歴書の中に面接官に質問してほしいキーワードをちりばめています。その結果、面接官がそのキーワードに基づいて質問を投げかけ、会話が弾むような流れができるわけです。こうした展開になる人は、多くの会社から引っ張りだこになることが多いです。
一方、履歴書や職務経歴書の内容を順番に淡々と伝える型通りの面接では、無難な質問だけが飛び交って終わりがちです。そのような面接はあまり成功しません。
お客様の「理想と現実のギャップ」を知ろう
営業の商談もこれと似たところがあります。
ポイントは、お客様が満たされていない可能性がある領域に関連するキーワードを提示することです。それについてお客様から質問やコメントをいただき、対話を深めるのです。
「お客様との対話が難しい」と感じる方も多いかもしれませんが、押さえるべきポイントは非常にシンプルです。「理想と現状のギャップが見えてきたら、それを丁寧に深掘りすること」、ただそれだけです。
理想と現状のギャップを見つける際には、いくつかのポイントとなる台詞があります。
理想と現状のギャップを見つける際にポイントとなるお客様の台詞
- 「本当だったら◯◯になっていなきゃいけないんですけどね…」
- 「不本意ながら◯◯することになって…」
- 「◯◯なことになってしまって…」
こうしたサインが出てきたときには、次のように深掘りしてみましょう。
![]()
営業パーソン
すみません、今の部分は重要かもしれませんので、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?
すると、お客様はより詳しく話してくれることが多いです。特に若手の方には、このように丁寧に深掘りしていくことをおすすめします。それだけで、お客様の「不」を理解することができます。
もちろん、その後に具体的な提案に繋げることになりますが、まずはお客様の「不」をしっかりと理解し、それをお話いただくことが重要です。
「お客様の『不』を理解するというスキル」を高めることに注力すると商談の質が変化します。それだけでも営業の成果は大きく向上しますので、ぜひ試してみてください。