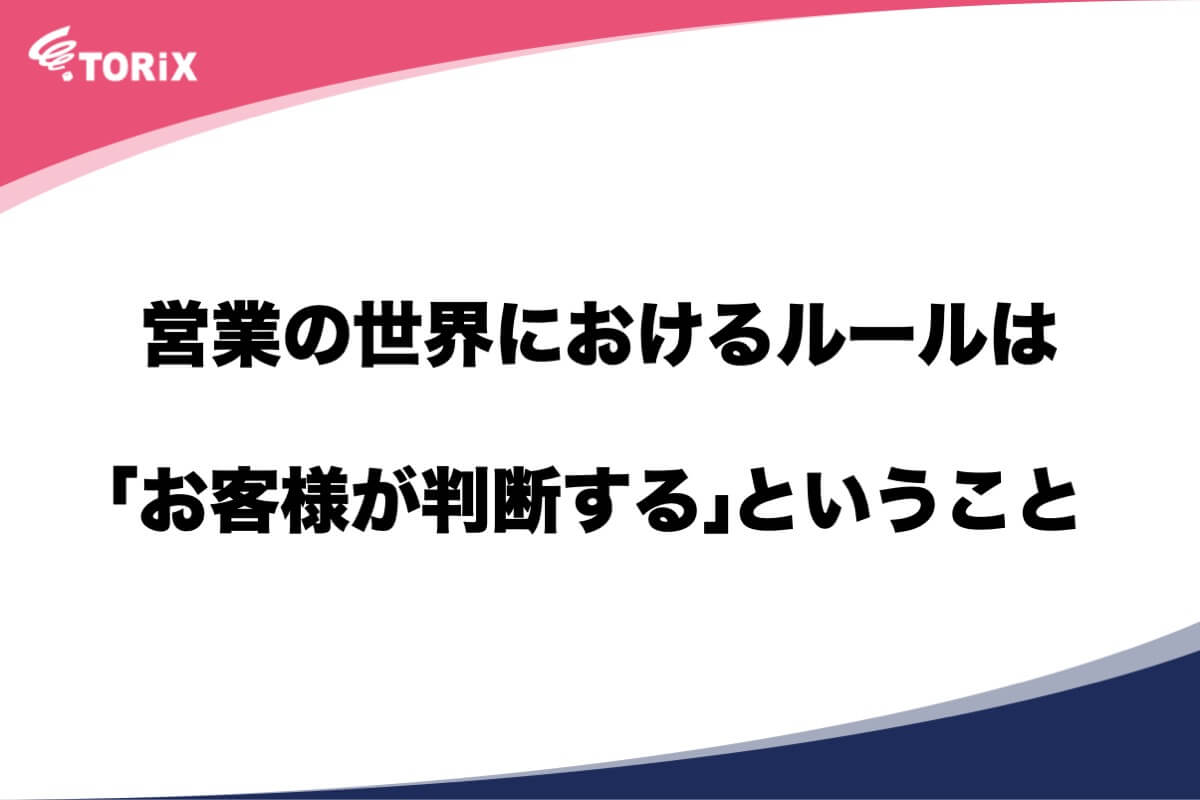営業が成長するカギは「遊び心」
今回は「営業の初期段階で身につけておくべき体質」についてお伝えします。
成長の余地、いわゆる「伸びしろ」は「遊び心」に影響を受けます。営業においてはただ堅実に努力するだけではなく、ある程度の「遊び心」がパフォーマンスの向上に寄与します。
企業で人材育成をされている方とお話をすると、よく耳にするのは「今どきの新人は正解を求めたがる」という声です。「今年の新人はどうですか?」と尋ねると、「優秀ですが、正解を求めるんですよね」と仰るのです。
「正解を求める」というのは、例えば困難に直面したときに何か1つの「正解」があると考え、その「正解」を上司や先輩に尋ねるということです。しかし、上司や先輩は「正解なんてないよ」と突き放してしまうことが多く、新人たちは困ってしまうのです。
これは若手の能力が不足しているのではなく、構造的な問題があります。現代は情報社会であり、ノウハウや知識が驚くべきスピードで流通しています。今の若手は常に膨大な情報に晒されてこれまでの人生を過ごしてきました。そのため、何か困難に直面した際に「正解となる情報はどこかにないか」と探すのは当然のことです。
しかし、もちろんどこまでいっても「これが絶対の正解です」と保証できるものはありません。そうなると、仕事ではどこかで自分でリスクをとって「ちょっと試してみようかな」と何かにトライしてみることが必要です。問題なのは、その「自分のリスクで試す」ことへのハードルがますます高くなっている点です。
最近では、ChatGPTやAIによって簡単にそれらしい答えを得られるようになっています。例えば、お客様に対して失礼のないメールを送る方法を考える場合、これまでは上司や先輩に相談したり、ネットで調べたりすることが一般的でした。
しかし今では、AIを活用するという新しい選択肢も増えています。AIを活用するとあっという間にそれらしいメールの文面が出てきます。しかし、それを「そのままお客様に送って良いかどうか」は別問題です。最終的には自分でリスクをとって判断する力が求められるのです。
「正解か、不正解か」という見方を手放そう
「正解/不正解」といった感覚に囚われると、際限がなくなってしまいます。「何がより正解なのか?」と考え始めると、どこまでいっても答えは出ません。
そこで必要なのは、発想を変えることです。
営業を一種のゲームのようなものとして捉えてみましょう。頭の中で、まるでゲームの中でレベルアップしていくかのように自分自身を成長させるのです。
ゲームにはルールがあるものですが、営業においてのルールは「お客様が判断する」ということです。「お客様が判断する」ということは、予測がつかない部分が多いのです。予測がつかない以上、何かを試してみて、そのフィードバックをもとに自分で考えていくしかありません。
「何かを試す」プロセスにおいて重要なのは「リスクを上手くとること」です。
例えば、致命的なダメージを受けるリスクがない状況であれば積極的にチャレンジし、新しい方法を試すことが重要です。しかし、失敗が許されない場面では自分がある程度信頼できる選択肢で勝負に出ることが求められます。
判断力を高めるには「リスクを取る技術」を向上させていくしかありません。
弊社代表の高橋は、新人を直接指導する場面ではまず最初に「回復不可能な損害」と「回復可能な損害」の違いを教えます。
例えば、「金額的にこの範囲までなら、何か問題が起こっても会社として許容できる」といった具体的な基準を示すのです。また、「お客様の前では何は許されて、何は許されないのか」の線引きを明確に教えます。これについては、繰り返し伝えることが重要です。新人が取れるリスクの範囲について、境界線を明示するのです。
初めは誰しも「自分がやっていることが良いことなのか、悪いことなのか」を把握するのは難しいです。もちろん最終的にはお客様がどのように判断するかが最も重要ですが、それでも横で見ている上司がフィードバックをすることは大切です。「こう感じたよ」と具体的なフィードバックを返してあげることが新人の成長につながるからです。
具体的なフィードバックがメンバーを成長させる
新人が「今日は全然うまくいきませんでした…」「やってはいけないことをやってしまいました…」と報告してきたときは、その失敗がどの程度深刻なものだったのかを数字で示すことが有効です。例えば、「一番やってはいけないレベルを−10としたとき、今日は−3くらいだね」といったように具体的な数値で示してあげると失敗の程度がわかりやすくなります。
リスクに対する感覚を身につけてもらうには、何らかのフィードバックを提供しないと理解できません。そのようなプロセスを経ることで、一種のゲームのように営業として成長していくのです。
上司がメンバーを見ているときにしっかりと指導しない限り、メンバーはなかなかスキルを身に付けることができません。場当たり的に気づいたことをコメントするだけでは、いつまで経っても自分で考える力が養われません。
自分なりに工夫し、試行錯誤を繰り返し、フィードバックをもらうことで「これが良かったんだ」と学んでいく。そうした感覚がある程度定着すると、その後はどんどん成長のスピードが加速していきます。