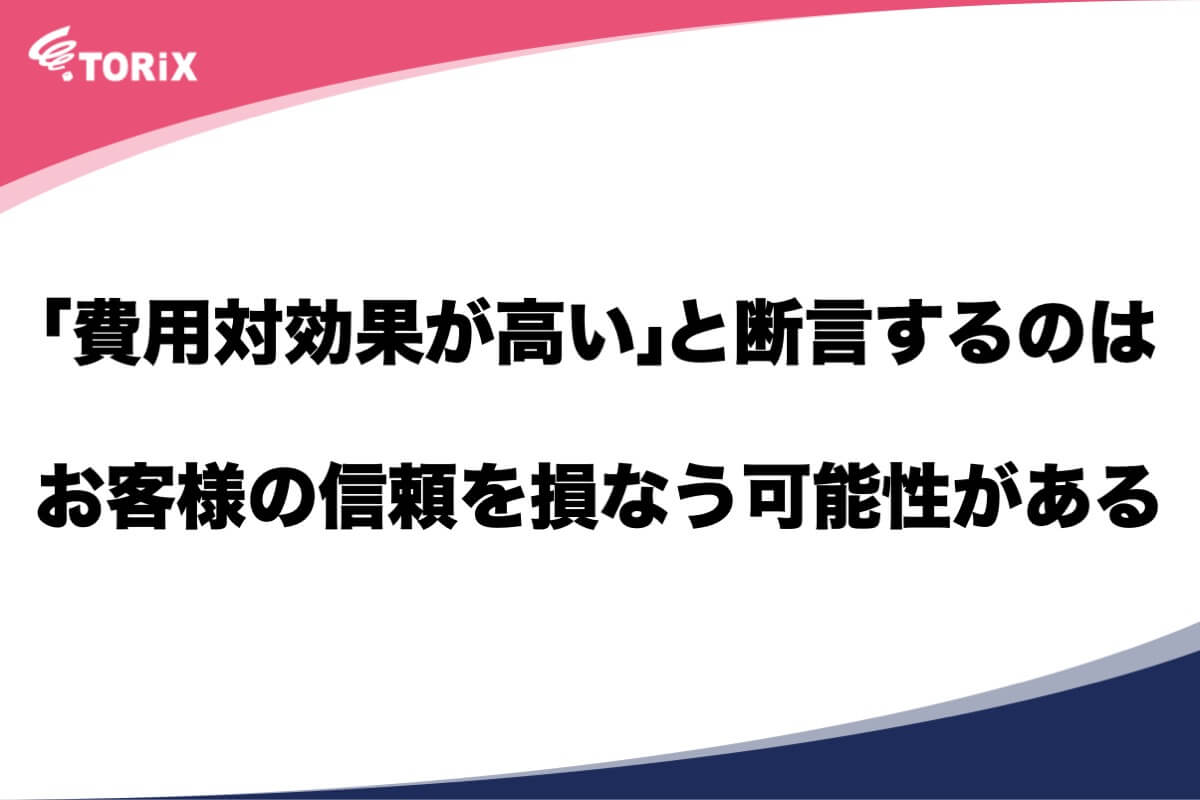費用対効果の説明において重要なこと
「他社サービスより費用対効果が高いことをどう示すか」は、よく相談を受けるテーマの1つです。一般的に挙げられる方法としては以下の3つがあります。
一般的な費用対効果の示し方
- ①ROI(投資対効果)の計算
フェルミ推定などを用いて、「このくらいの効果が期待できます」と試算する方法です。 - ②機能比較表
他社サービスとの違いを、機能を軸としたマトリクス形式で示すものです。 - ③効果が出た事例
実際のお客様のケーススタディを紹介し、「こういった結果が得られました」と具体例を提示することです。
これらの方法は基本的なものとして知られていますが、他社も同様の手法で「良さそうな情報」を提示してくるため、お客様はどのサービスを選ぶべきか決めかねることが多いのが現実です。
上記の基本的な方法に加えて、以下の3つの情報を組み合わせることで、お客様に対して費用対効果をより明確に訴求することができます。
①特に御社がフィットする理由
「ユーザーとして、御社は効果が出しやすい条件を備えています」と説明しましょう。
![]()
営業パーソン
弊社のサービスは、特定の機能や設計思想に基づいて作られています。そのため、業種、商材、組織の規模によって適合性に差が出る場合があります。しかし、御社の状況は弊社サービスの設計意図に非常に適合しており、効果を出しやすい環境にあります。
②効果が出にくいタイプのお客様を明示
「こういった条件のお客様は効果が出づらいです」と伝えましょう。
![]()
営業パーソン
弊社はこれまで●●社のお客様にサービス提供してきました。その中で、うまく効果が出せたケースと、そうでないケースの両方がありました。このようなタイプのお客様は、正直に申し上げて、効果が出づらいです(逆に言えば、そうでなければ大丈夫です)。
③上手な使いこなし方のレクチャー
「このサービスを最大限に活用するための具体的な方法」を提示しましょう。
![]()
営業パーソン
当社のサービスを使いこなしていただくにはコツがあります。具体的には、5つのポイントがあります。1つ目の点は…
①〜③のいずれの場合にも、重要となるのは「翻訳力」です。情報をお客様が受け取りやすく、納得しやすいように伝えることが重要です。
「高い費用対効果を出すことの難しさ」と向き合おう
冒頭に挙げた「一般的な費用対効果の示し方」はどれも有効な面はあるものの、「落とし穴」もあります。営業が「費用対効果の高さを証明しようとしてしまう」のです。
一見すると、「費用対効果が高いと示せれば売れやすい」と考えるのは自然なことです。しかし、冷静に考えれば、購入前にその効果を完全に保証するのは非常に難しいという現実があります。実際には、どれだけシミュレーションを重ねても、100%費用対効果を保証することは不可能です。
さらに重要なのは、費用対効果が高いかどうかは、お客様自身の取り組みに大きく左右されるということです。営業がどれだけサポートをしても、導入後の活用方法によって結果は変わってしまうのです。
例えば、ユニクロのヒートテックについて考えてみます。ヒートテックは非常に温かく、「この価格で、これだけ温かさを感じられるなら安い」と思える商品です。しかし、当たり前ですが、実際に着ないことにはその温かさを実感することはできません。また、毎日温かく快適に過ごすためには、ある程度の枚数を購入し、日々洗濯をする必要があります。
このように、どんな商品であっても、その効用を得るにはある程度購入者側の努力が必要になります。これが無形商材のサービスになると、お客様側に求められる努力の度合いが一層大きくなる傾向があります。
その点を踏まえると、「費用対効果が高い」と営業側が断言するのは、かえって信頼を損なう可能性があります。なぜなら、高い費用対効果を実現するには、お客様自身の取り組みが必要不可欠だからです。
そこで重要なのは、「費用対効果を示すこと」ではなく、「費用対効果を出すことの難しさと向き合うこと」です。なぜなら、費用対効果を出すのは決して簡単なことではないからです。もしそれが簡単にできるのであれば、営業が苦労することなく商品はどんどん売れていくはずです。
お客様自身に努力をする意思がなければ、高い費用対効果が実現することはありません。だからこそ、「費用対効果を出す難しさ」に営業側もお客様側もきちんと向き合う必要があります。営業もお客様も、それぞれの立場でこの課題に向き合うことで、より良い結果に結びつけることができるのです。
重要なのは「相性の良いお客様」を明確にすること
そこでまず大切なのは、「相性」をしっかりと認識することです。商材が適しているお客様と、そうでないお客様を明らかにするのです。この「相性」を営業が正確に把握し、それをお客様の気分を害することなく適切に伝えることが重要です。
例えば、成果が出やすいタイプのお客様であれば、その特性を具体的に言語化して伝えます。一方で、そうでないお客様には、「慎重にご検討ください。このような条件のもとでは効果が出にくい可能性があります」といったように、事前に注意点を共有することが重要です。
弊社では「フィット感のあるお客様の7箇条」という基準を設けています。この7箇条は、例えば「単純に講演を聞くだけで成果を期待するのではなく、一定期間腰を据えて取り組む姿勢を持っている」といった、成功に必要な条件を具体的に挙げたものです。
この基準をもとに判断すると、7つすべてに該当するお客様は非常に成功しやすいと言えます。一方で、5つや4つ該当するお客様はある程度の努力が必要となり、3つや2つしか該当しない場合は成功するのが難しいという傾向があります。この基準を全社で共有することで、営業活動の質が高くなります。
実際には、お客様にこの基準をそのまま露骨に伝えるわけではありません。しかし、営業チーム全体でこの基準を認識していれば、自然と成功しやすいお客様に時間を多く割くようになります。そして、成果を出しにくいと予想されるお客様には時間を控えめにすることで、結果的に「相性」の良いお客様の成功をサポートしやすくなります。
さらに、この「相性」を営業が提案段階でうまく伝えることができれば、お客様も安心感を持ちやすくなります。また、購入後の利用に向けた心構えを持つきっかけにもなるでしょう。
「お客様の成功」が「良い循環」を生み出す
「費用対効果を出せるかどうかはお客様次第」です。
もちろん、これを営業が一言で済ませてしまうのは問題です。「成功するかどうかはお客様次第です」とだけ言われてしまえば、お客様は「それなら営業の存在価値ってなんなの?」と感じるはずです。「ただ正論を言っているだけで、営業はなにもしてくれないのか」と思われてしまうでしょう。
そこで必要なのが、お客様が商品をうまく使いこなすための具体的なガイドを提供することです。これは、商品やサービスを最大限に活用していただくための「取り扱い説明書」のようなものです。このようなガイドを提供することで、営業としての付加価値を高めることができるのはもちろんのこと、なによりもお客様の成功確率を上げることができます。
「こういったカスタマーサクセスのミーティングを設定しておくと効果的ですよ」「このように現場を巻き込むことで成功しやすくなりますよ」といった具体的な商品やサービスの使いこなし方を伝えるのです。
「成功するためにはこうした方がいい」というガイドをきちんと提供することが大切です。このような説明を行わずに販売してしまうと、最終的にお客様の成功確率は低くなってしまいます。お客様の成功確率が下がると、営業は自信を持って商品を売れなくなります。
お客様が成功しているからこそ、営業もお客様も費用対効果を実感することができます。そして、その実感が次の販売に繋がります。費用対効果をうまく提示できれば、売れるようにもなります。お客様の成功はそのような「良い循環」を生み出してくれます。
「見せ方」よりも「お客様の成功」に意識を向けよう
しかし、費用対効果の高さを一生懸命に説明したり、その「見せ方」を工夫しすぎたりすると、この「良い循環」から外れるリスクが生じます。
人の時間やエネルギーには限りがあります。費用対効果を「良く見せようとすること」や、「どうすればお客様が納得するか」といったことは、本筋とは関係がありません。
重要なのは、お客様の成功です。それには購入後にお客様がどのように取り組むか、また営業がどのようなサポートをするか、といったことが大切です。費用対効果の巧みな見せ方は、そういったこととは全く関係がありません。
営業が陥りがちな罠は、費用対効果について「どうやってうまく訴求するか」に時間とエネルギーを使い過ぎてしまうことです。本当に大切なのは、費用対効果を出す難しさと正面から向き合うことです。
そのためには、まず最初にお客様にも「相性」があることを理解してもらうことが重要です。成功しやすいタイプのお客様もいれば、成功しにくいタイプのお客様もいるという現実を理解していただくのです。営業側としても、初期段階で成果を出しやすいお客様にリソースを集中することができるようになれば、質の高い営業活動ができます。
そして、お客様に適切なガイドを提供し、「成功させる覚悟」を持ってもらうことが大切です。営業には、お客様が実際に動こうと思えるようにサポートし、成功するまで伴走しながら支援をすることが求められます。
このように考えると、「費用対効果をどう見せるか」という問題は、だんだんと小さな問題に感じられてくるはずです。